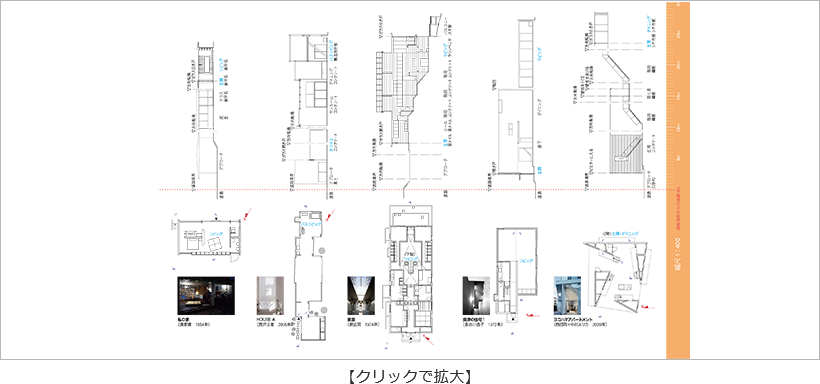玄関から考える住宅の可能性(後編)
玄関が変えるまちと住宅
原田真宏(建築家)× 武井誠氏(建築家)× 門脇耕三(建築学者、進行)
『新建築住宅特集』2015年10月号 掲載
既存の玄関の空間やつくりを捉え直す
門脇:
では次におふたりの印象に残る玄関を教えていただけますか。
原田:
まず、ウィトゲンシュタインの「ストンボロー=ウィトゲンシュタイン邸」の玄関です。ここで使われている片開きのガラス框戸には取手が縦方向の真ん中に付いていますが、そのことで空間の尺度が失われ、スケールが分からなくなっています。僕の場合だと、逆に取手の位置を低くして、気積を大きく知覚させることがあります。また手触りのある工業製品の使い方という点でも優れていると思います。
門脇:
外部からの視点に立った場合にも、建物の大きさや街との距離の感じ方を調整するのに使えそうな手法ですね。



原田:
まず、ウィトゲンシュタインの「ストンボロー=ウィトゲンシュタイン邸」の玄関です。ここで使われている片開きのガラス框戸には取手が縦方向の真ん中に付いていますが、そのことで空間の尺度が失われ、スケールが分からなくなっています。僕の場合だと、逆に取手の位置を低くして、気積を大きく知覚させることがあります。また手触りのある工業製品の使い方という点でも優れていると思います。
門脇:
外部からの視点に立った場合にも、建物の大きさや街との距離の感じ方を調整するのに使えそうな手法ですね。
原田:
また、アントニオ・ガウディの弟子であったジュゼップ・マリア・ジュジョールが設計した農村に建つ住宅「カサ・ボファルイ(Casa Bofarull)」では、農器具の鉄部が取手になっている建具をはじめ、住宅全体がブリコラージュ的にできていてます。僕が違和感を感じるのは、どの地域でもアノニマスな玄関ドアが並んでいる風景です。標準化や大量生産という発想を、たとえばセミオーダーができるようなシステムが加わることによって、そこに何か土地のエッセンスを含ませることができれば、住宅地の風景も土地に根ざしたものに変化するのではないでしょうか。造船会社の社宅であった「Seto」(『新建築』1308)では、鉄板を造船工場に持ち込んで、玄関ドアをあぶって3次曲面の引き手としましたが、これは撓鉄(ぎょうてつ)という造船技術を使用したものです。玄関ドアという設えでも、そこに暮らす人が見えるようになると街が楽しくなるように思います。またカルロ・スカルパの玄関扉も、イタリアの工芸品のようなデザイン密度でつくられていて魅力的です。ヨーロッパでは骨董品店に建具が売られていることがありますが、そのように代々使っていくことを前提とした、ビンテージになるような扉のつくり方ができると素敵ですよね。
門脇:
製品化された玄関ドアについても、その土地に根ざした要素を加え、設えによって地域性を示すという方法は可能性がありそうです。原田さんは、工芸的なつくり方を部分的に取り入れた生産方式が、これからの部品産業を主導していくとお考えですか?
原田:
そうですね。現在の情報処理と結びついた生産技術であれば十分可能だと思います。セミオーダーシステムはスニーカーなどですでに実現しているし。せっかくつくるのなら、ドアノブやヒンジといった小さな部品をきっかけにしてでも、時間が経つことでよいものになる存在であってほしい。たとえば店舗用のアルミサッシはフロント材によるセミオーダーでつくれますが、住宅になるといきなりハードルが上がる。それを下げるために、機能的な仕様条件にもう少しゆとりを設ければ、可能性が広がるのではないでしょうか。
門脇:
そうですね。単体の部品で性能を担保するだけではなく、部品の性能をほかの部分で補うような考え方もあるのだろうと思います。
では、武井さんの印象に残る玄関もお話いただけますか。
武井:
僕はまずアマンシオ・ウィリアムズの「小川に架かる家」(『a+u』臨時増刊号『20世紀のモダン・ハウス:理想の実現 I』)が印象に残っています。小川が流れる敷地に建つこの住宅は橋を置く必要があり、橋そのものを住宅にしています。その橋脚を玄関にしていて、自然が広がる地面と室内の高さ関係に面白さを感じます。また、地面との高さ関係は玄関の性格を決定付けると思いますが、それを都市の視点で見てみると、丹下健三の「住居」(『新建築』5501)と菊竹清訓の「スカイハウス」(2に図解/『新建築』5901)のような地面とプライベート空間の関係に魅力を感じます。丹下さんの自邸である「住居」は庭の存在が効いていて、その後「広島平和記念資料館」(『新建築』5606)や「香川県庁舎」(『新建築』5901)で展開するピロティによって外部を1階に挿入する手法を住宅スケールでも実現していると思いました。
門脇:
住宅の主要部を2階に持ち上げる形式はヴィラでよく見られ、日本では大正期にはそうした作品が見つかりますが、戦後の建築家は都市で実践した。郊外住宅の形式が都市住宅に転用されたのだと思います。


武井:
ただ近年、限られた敷地面積の都市環境に建つ現代住宅では、このような形式はあまり見られません。しかし縮小化していく社会において、パブリックな空間が住宅内部に入り込む形式には可能性があると思い、今ピロティをもつ住宅を東京で設計しています。
原田:
近々日本は人口7,000万人の社会がくるかもしれない。そうするといまの4割程度の空きフロアができ、高密集中型ではなく低密分散型の社会になっていくかもしれません。その空いたスペースを利用して、住宅の中に社会をとりこむ手法は可能性があると思っています。
武井:
その場合、街との境界はもっとルーズな仕切りでよいと思うのです。たとえば山本理顕の「山川山荘」(『新建築』7808)は、別荘ではありますが、必要な場を最小限につくり内部と外部を混合しており、一般的な玄関がありません。自然の中に建つこの住宅の形式が、現代では都市に建っていても不思議はないのかもしれません。ただ大きな外部をつくる時に問題になるのは外部は面積に含まれないので、非常に小さな床面積になってしまいます。同じコストをかけても坪単価が高くなってしまい、印象がよくない。たとえば賃貸住宅であれば、外部空間を加味した家賃設定などは難しいでしょう。しかしこの形式は、空間を細分化することもできるので、必要に応じて空調をすればよいわけで、ランニングコストは非常に下がるなどのよい点もあります。ですから既存の評価軸を考え直し、今ある空間の価値への概念を崩さないといけないと思います。
門脇:
住宅は、性能も家賃も内部空間だけで評価されて、価値付けされているのが現状です。ですから、内部空間をできるだけ確保して、その性能を担保することばかりが主軸となり、半外部的な空間がとてもつくりづらい。そこを突破できる方法を見つけていけるとよいと思います。
このコラムの関連キーワード
公開日:2015年09月30日