パブリック・スペースを創造する 4
ポストコロナの社会で未来像はいかに描けるか
山崎亮(コミュニティデザイナー) 聞き手:浅子佳英(建築家、タカバンスタジオ)
地域モデルの時代の介護施設
浅子
厚労省の主導で地域包括ケアシステムが推進され、医療・福祉の現場が地域とのつながりを強めていくなかでハードルとなったのはどのような部分でしょう。また、現在ではどのようなことが課題となっているのですか。
山崎
これまで話した流れは、「医学モデル」から「生活モデル」へと移り変わっていく過程でした。現在はさらに「地域モデル」へと移行しつつあります。医学モデルというのは、身体の悪いところを見つけてそこを直そうという考え方で、措置の時代と重なります。それが介護者の生活全体を見ていかなければいけないと言われるようになり、そのためには措置ではいけないとされて契約に切り替わったというのが2000年代初頭でした。生活モデルは「ストレングスモデル」と言われることもあるのですが、これは介護者本人の強みを伸ばして自立支援につなげようとする考え方です。それまでのリハビリは高齢者が不自由しがちな上腕や指先の機能を改善させるために、塗り絵などをやってもらうのが一般的でした。しかし、回復の度合いは人に応じてさまざまです。例えば、その人が鮨職人だったとしたらどうでしょう。最も得意とする「握ること」が結晶型知能として残っているならば、その動きをリハビリで取り組んでもらうほうがはるかに効果は期待できるわけです。つまり、生活モデルやストレングスモデルで考える場合、その人が現役時代に打ち込んできた仕事や生活パターンに着目することが重要になります。それを行うには、入居する介護施設を専門家が一方的に決めるのではなく、本人の意志を尊重しなければならないとされたことで、措置から契約の時代へと移り変わっていきました。
とはいえ、契約の時代も利点ばかりではありません。問題のひとつは本人の意志を尊重するつもりが、家族の都合で入居施設が決められてしまう実状があることです。その結果、本人が帰りたくとも帰らせてもらえないといったことも起こっている。これを乗り越えることが今もなお課題として残されています。こうしたなか、本人の意志を尊重しつつ、家族の負担を減らすための解決策として出されたのが地域モデルであり、地域包括ケアシステムの考え方でした。
では、地域モデルの時代にどのような介護施設が求められるのか──。ここで理想とされるのが、地域の人たちも気軽に利用できるようなデイサービスのイメージなんですよ。例えば、あるおじいさんが日中、デイサービスに出かけるとしますよね。そこに地域の人の出入りがあれば、見る見られるの関係のなかで適度な交流も起こって、おじいさんもほどよく落ち着いて過ごすことができる。そういう環境に身を置くことで身体もそこそこ疲れるので、夜はぐっすり寝られる。そうして次の日も安心して出かけられれば、家庭の負担も増えずに済むし、地域の人がいてくれることで介護施設の職員も四六時中ケアしなくてはならない状況から解放されます。そのためにも、介護を必要としない地域の人たちが無料で入り浸れるようなスペースをつくろうというのが地域モデル時代の介護施設の流れです。
ただ、こうした空間を施設内に取り入れようとして、福祉の現状をわかっていない設計者が介入した結果、まったく使われないスペースになってしまう例もあるんです。あいまいなようで福祉の観点で見れば明確な目的をもった、非常にセンシティブな問題なので設計にも勉強が必要なのですが、そこまで時間を割く余裕がない設計者も多い。介護の人たちもわかってほしいから一生懸命話してくれるんですよ。でも、なかなか伝わらない部分もあり、結果、がっかりさせてしまう。地域の人たちがわが物顔で使い倒してくれるスペースをつくるという問いの立て方は悪くないんです。実現の仕方がわからないだけなんです。
でも、僕たちに言わせれば、それほど難しいことではないと思う。外から入りやすい場所にお茶やお菓子を置いて過ごしやすくしておけば、地域の人たちはふらっと立ち寄って世間噺に花を咲かせてくれるはずなんです。これはグループホームではなく医療施設の例ですが、studio-Lが北海道の沼田町でお手伝いした「クリニックと暮らしの保健室」のプロジェクトでも、地域のスペースをつくるために、ワークショップを開いて地域住民の方々と話をしました。するとみんな、使いやすいテーブルがあっていつでもお茶が飲めるなら毎日でも通うわよと言ってくれる。だから僕たちも、本当に通ってくれますね?と念を押すんです。地域の人たちが確約してくれたものをあとは図面化すればいい。「クリニックと暮らしの保健室」は古谷誠章さんとスタジオナスカの協力もあり、オープン後は本当にそういうスペースが実現しました。これがグループホームであれば、編み物をしたりダンスをしたりと、自分たちのリビングであるかのように使ってもらうこともできる。結晶型知能が残っている入居者に洗濯物を畳むのを手伝ってもらえれば、リハビリにだってなるかもしれない。こんなことががっちりと組み合うと、いいことずくめのはずなんです。地域モデルとしての介護の空間は実現できるので、実際にそのプロセスを知りたいといって僕たちに声をかけてくれる人たちがすごく増えています。

studio-Lが手掛けた北海道沼田町の「クリニックと暮らしの保健室」。
地域に開かれたスペースはカフェさながらの憩いの空間
提供=studio-L

「クリニックと暮らしの保健室」のためのワークショップ。
設計者も参加し、さまざまな意見が交換された
提供=studio-L
大きなビジョンをつかむ力
浅子
ものをつくるところから離れ、コミュニティデザイナーとして新しい領域を開拓したはずの山崎さんが、一周まわって、再び空間をデザインするところに戻ってきたような感じですね。僕にとって今のお話は、泉佐野丘陵緑地のプロジェクトで切り開いた新しい現代的な設計手法をバージョンアップしたもののように聞こえました。緑地の運営計画にしても、高齢者を抱える家族や地域の課題にしても、これまでの設計では解決できないことばかりです。そのようななかで、山崎さんは一歩引いて周囲を見渡し、その後の使われ方やつくる前の人々の関わり方までをも考えるパレットに上げることで、実現可能なビジョンを示すことになった。もののデザインから離れたように見えて、実際は設計の概念を拡張して大きな見取り図を描いているように見える。それこそが大きな意味での設計と言えるのかもしれないと思いました。
そして僕は、こうしたビジョンの描き方が建築家のリサーチの問題にも関わるように思えるんです。というのも、昨年3月にstudio-Lが主催して「おいおい老い展」が開催されましたね。この展覧会は、全国から集まった500名の参加者との「これからの介護や福祉を考えるデザインスクール」の成果がもとになっています。この図録のなかで山崎さんは「バックキャスティング(目標にもとづいて今すべきことを考える方法)」でデザインスクールを行ったと語っています。ワークショップはふつう「フォアキャスティング(現在を起点として未来を予測する方法)」で行うものですが、ここでは参加者が「なりたい自分」に向かうためにバックキャスティングを用いたという。こうした考え方は今、建築の設計でこそ有効なように思えます。なぜなら、現代の建築家はリサーチの問題を一生懸命考えすぎて、ビジョンを描けなくなっているように感じるからです。例えば、COVID-19の影響でリモートワークをしている多くの人が職住一致の便利さを感じていると思います。できることならこのままがいいと考えている人も多いでしょう。しかし、住宅地にオフィスビルを建てるのは法規の問題で難しい。だから、住宅や住宅地のリサーチをしても法律はその外側にあって見えないものなので、そこを変えることはできず、いつまでたっても街の風景からかたちを引っ張ってくるといった現状維持の解決策ばかりが生まれてしまう。現在のような時代のなかで流れを大きく変えようとするなら、バックキャスティングによって大きなビジョンやモデルをまずは描かなければならない。
とはいえ、いささか山崎さんの話を聞くことに徹してしまっているので少し反論もさせてください(笑)。最近のCOVID-19の報道を見ていると、恐怖や不安をあおって行動を促すような論調が目に付きます。僕はこのやり方が正しいと思えません。やはり明るいビジョンによってよくなる方向を指し示すような姿勢であるべきだと思うんです。他方で、良質な人のつながりとか、関係性の好ましさを頭から信じ込むのもどこか疑わしい。というのも、そうしたものにこそ格差というものは現れるからです。例えば、良好な人づきあいというのは経済的な豊かさがあるところに多く存在しがちですし、アメリカなどで犯罪率の高い地域やスラムに暮らす人々は良質な人のつながりが持てない場合が多い。社会の流動性が高まることには、女性の雇用機会が増えたり、人種を問わず参政権が認められたりといったいい面もありますが、人のつながりのよさみたいなものを手放しに是とする風潮はかえって社会を息苦しくするおそれもあります。
山崎
コミュニティデザインがつながりをつくる仕事だと理解されると、そういう批判も無理からぬことかもしれません。でも僕たちは良質なつながりをつくりたいと思ってはいるものの、けっしてそれを仕事にしているわけではないんです。というのも、studio-Lは行政から発注を受ける立場だからです。行政は人のつながりづくりに予算をつけてくれるわけではない。成果物は最終的に設計図面や総合計画、産業振興ビジョンといったものに結実していきます。その過程で他のシンクタンクとは違ったプランニングができるし、公共施設がオープンしたら第一陣としてそこを使いこなしてくれる地域住民を育てることもできるんです。その部分は行政にとっておまけのようなものにすぎないものですが、それがあることで他の事業者にはできないプランニングが可能になるのも事実です。
浅子
たしかに、ご著書のなかではコミュニティをデザインするのではなく、コミュニティによってデザインすると言っていますね。
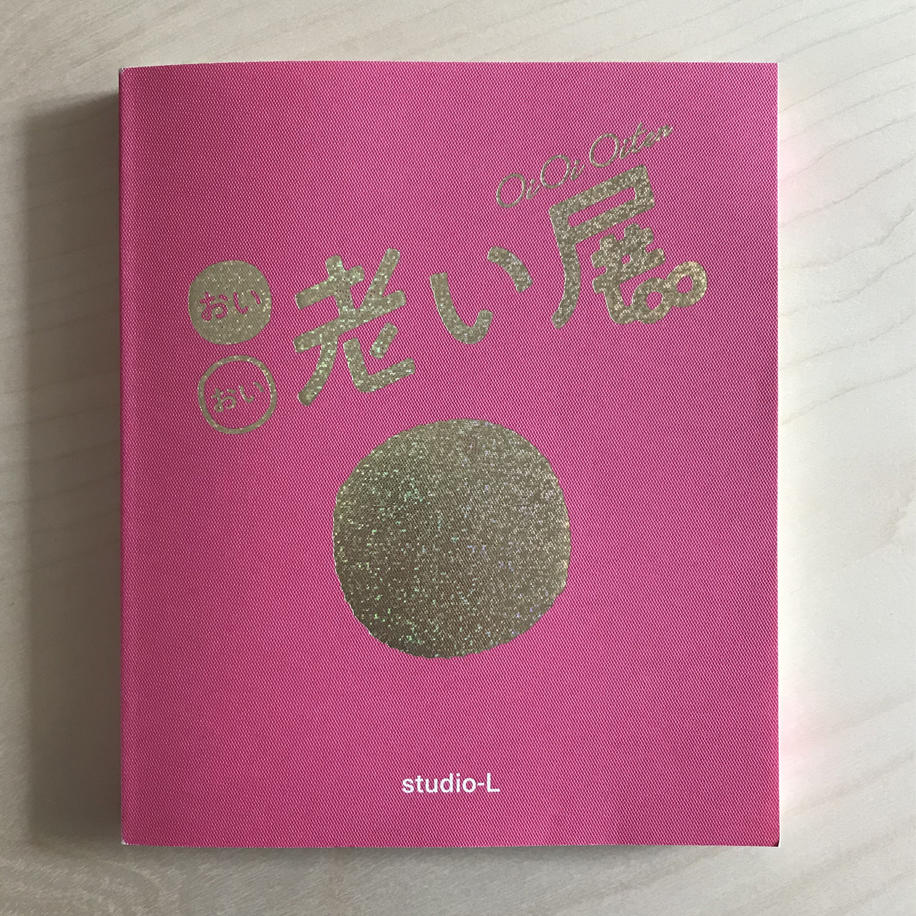
studio-Lが主催した「おいおい老い」展カタログ(studio-L、2019)
山崎
まさにそうです。僕らが神の手のようにコミュニティをつくっているわけではない(笑)。コミュニティデザインという言葉は和製英語のようなニュアンスがあって、実際にアメリカ人に尋ねると「コミュナル(集団的な)デザイン」だと言われます。それを誤解されると「つながりをつくっている」と捉えられてしまんです。
浅子
わかります。でも、山崎さんのお話を伺っていると「良質な人のつながりを失いつつある」といった表現がたびたび用いられるのも事実ですよ(笑)。だから、誤解を誘引しているところもあるのではないかと思う。もちろん人を惹きつける言葉がなければ、関心を呼ぶこともできないので必要に応じてということかもしれませんが。
山崎
今お話したように僕たちがやっているのは計画づくりだったり、チームメイキングだったりするんですが、結果的にいつも人のつながりが生まれているのも事実です。僕たちが地域から撤収した後、地域のおじいさん同士で会社を立ち上げたり、ワークショップの参加者同士が再婚したり、元農家の人が料理人とつながって農業を再開したりといったことがとても多い。今まで全国の約250地域で仕事をしてきましたが、つねにどこかで新しい動きが起きています。
浅子
そういう新しい展開がスタートするのもやはり、地域の人が自分たちで正しく考える力を身につけているからですよね。このCOVID-19の社会状況を見ると、今こそコミュニティデザイン流の自走モデルが求められている気がします。先ほどのデイサービスの例のように、地域の人たち同士が協力しあえる社会が実現すれば、マスクの備蓄がある人は足りない人に分けてあげたり、自宅にこもっている高齢者に食事を届けてあげたりといった行動も自然に生まれるかもしれない。とくに少子高齢化で財政的にも苦しくなることが予測されるなか、医療だけに頼らず、地域で健康でいることができる仕組みづくりというのはますます重要になるでしょう。今回山崎さんに話を聞きたいと思ったのも、こうしたヒントがもらえるかもしれないと期待したからです。
ハワード再考──職住近接の郊外は可能か
浅子
ところで、最初に話題に挙げた『コミュニティデザインの源流』の話に戻ると、モリスは分業を嫌ったという話が登場します。それは僕もよくわかるんです。設計の仕事をしているとその建築だけではなく、場所にも愛着が沸いてくるのでリサーチからデザイン、基本設計、実施設計、現場監理、引き渡し後のリサーチまで、すべて関わりたいと思う。でも現代人には、ある部分は優秀でもある部分ではそうじゃないというように、強い個人像への期待に応えられない面もあります。平野啓一郎さんが、『私とは何か』(講談社現代新書、2012)のなかで「分人」という言葉を用いて説明されていたような人間像のほうがどこかリアルに聞こえる。ひとりのなかにもすこしずつ違う側面を持っているのが今のリアルな人間像であって、すべてを個人に帰結させるほうが幸せだと言われると、非常に強い近代国家の時代の近代人としての人間像につながってしまうように感じられます。もっと適当かつバラバラで、弱い人たちばかりでもかろうじて廻るような社会のほうがいいんじゃないか。というわけで、モリスも山崎さんも理想が高すぎませんかね。
山崎
モリスの理想が高いと感じるのはおっしゃるとおりだと思います。だからモリスや、その師匠筋のラスキンやオウエンなどは、のちに登場したマルクスやエンゲルスたちから空想的だと言われてしまった。そういう意味で、これからちょっと違う見方を試しに説明してみようと思うんですが、じつはモリスの分業批判は理想を低くするつもりで言っているのではないかと思うんですよ。つまり、弱い人間同士が優れている部分を組み合わせれば最高の社会になると言っているように僕には聞こえるんです。そう考えると推奨されているのは分業禁止ではなく、レベルを下げることではないか。例えて言えばstudio-L。僕たちはすぐれた個人の集まりではなく、どこか中途半端な個人がそれぞれ得意なことを持ち寄って組織の体を成しているんです。studio-Lでは分業禁止令を敷いていますが、これはそこそこのレベルでも全員が協働を楽しめるようにという提案でもあるんですよ。そして、こういう組織のほうがワークショップの場でも好都合だったりする。なぜなら、何でもできるスーパーマンでは住民がやる気をなくしてしまうからです。完全無欠のファシリテーターがいると参加者の主体性が損なわれ、最終的にstudio-L頼みになってしまう。それよりも、中途半端な僕たちを見た地域の人たちが、「あんたら大したことないな」と言ってくれるほうがとてもありがたい。そう言われれば、「だからこそ、地域で暮らすあなたたちの力が必要なんだ」と返すことができるし、そうでなければ僕たちの仕事は進まないんですよ。
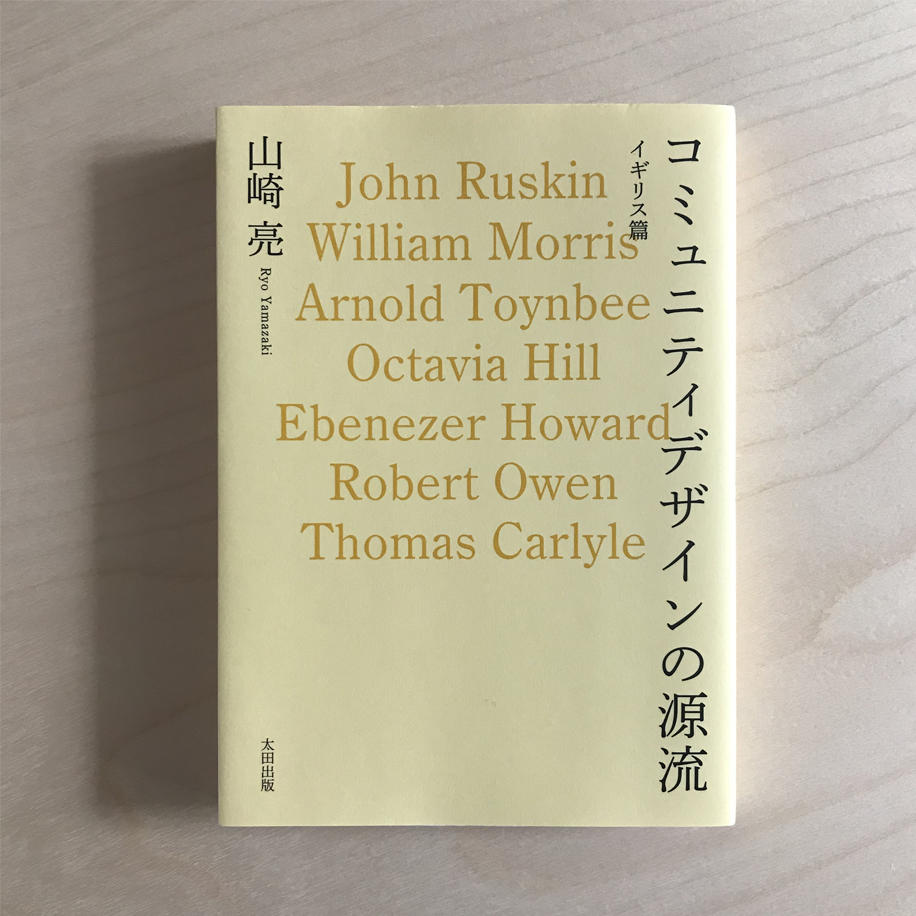
『コミュニティデザインの源流』(太田出版、2016)
浅子
よくわかります。しかし、謙遜しすぎではないですか。今のレトリック自体、山崎さんしかできない相当な話術でしょう。ちょっと意地悪かもしれませんが、『コミュニティデザインの源流』のなかでも仕事のあらゆるところに美しさを入れ込む努力が必要だと書いてありましたよ(笑)。
山崎
もちろん、そういう気持ちはもってもらいたいと思いますけどね(笑)。でも、それは完璧にデザインしろと言っているわけではないんですよ。studio-Lには、グラフィックのことばかり考え続けることができるグラフィックデザイナーがいるわけではないので、どうがんばってもグラフィックデザイン界の最先端を突っ走ることはできない。あくまで僕たちの仕事の範囲でいいものを出そうということです。うちの場合、全員が写真も撮らなければいけないし、人前で話さなければいけない。ファシリテートする仕事もあれば、模造紙に付せんを貼る仕事もある。それぞれがすべてをこなさなくてはならないなかで、すべての分野で先端を突っ走ることは不可能なことです。でも、どの分野も「そこそこできる」というのが、ワークショップの現場では住民のやる気を引き出すんです。ただ、最先端を望む人が弊社にインターンでやって来るとがっかりされたりもしますよ。
浅子
手法ばかりが新しくなって人々が付いてこられないとしたら本末転倒ですからね。『コミュニティデザインの源流』の話に関連してもうひとつ言うと、僕はエベネザー・ハワードの田園都市論こそ今注目すべきだと感じたんです。モリスをはじめとするハワード以前の活動家にとって未来の都市像を実現するためには革命が付き物だった。革命とまではいかなくとも、古い都市の破壊とセットだった。ところが、ハワードはそれらとは違う都市像を提案した。ロンドンから離れた土地に職住兼ね備えた町をつくれば、既存のロンドンの公害や都市居住の課題もおのずと解消されると考えたわけです。これはすべてを更地にして再開発する流れや、リノベーションによる漸進的な改良以外に方法がない現代に、違う選択肢を与えてくれるものだと僕は思うんです。先ほどから言っているように、ビジョンを描かなければ未来がないような状況で、とくにCOVID-19によってリモートワークの実効性もある程度明らかになった今は、毎日満員電車に揺られる生活スタイルを見直す機会でもあります。だから今こそハワードの田園都市モデルはもう一度見つめ直す価値があるのではないか。
そこで残念なのは、この田園都市モデルが日本では田園郊外に翻案されてしまったことです。阪急の小林一三が手掛けた鉄道敷設と住宅地開発が、五島慶太の東急によって引き継がれたことが、日本における郊外化の大きな流れをつくったと言ってもいいと思うのですが、それが今、団地を中心とした急速な郊外の高齢化という課題を浮き彫りにしている。田園都市の利点は田園-都市、つまり、働く場所と住む場所を兼ね備えていたことであって、僕たちはそれらが分離したなかに置かれてしまっています。今日、最後に山崎さんに訊いてみたかったのは、仕事もできる住宅地のようなものを新しいビジョンで展開できないかということです。それはコミュニティデザインの活動を通じてハードとソフトを一緒に考えている山崎さんのビジョンにもつながるし、さらに言えば、医療・介護分野の地域モデルにも含まれる問題系だと思います。職と住が近い距離にあれば、高齢の親の介護を嫁任せにするといったこともなくなる。ユートピアとも現実主義でもない、リアルなビジョンを今描くことはできないでしょうか。
山崎
田園都市が田園郊外になったというご指摘はおっしゃるとおりです。ハワードの田園都市構想には有名な「3つの磁石」の図があるのですが、これは「都市(Town)」「農村(Country)」「都市・農村(Town-Country)」の三極が磁石で人々を引き寄せ合うことを描いたものです。ハワード自身は革命志向ではなかったものの、それ以前の社会主義者からも強く影響を受けているので、土地はすべて田園都市を営む公社の所有にすると書いています。借地にすることで賃料をまちのマネジメントに充当するというアイデアからも明らかなように、ハワードは経済のことも考えながら構想を組み立てていました。こうした考え方をそのまま実現するのは無理だとしても、田園郊外としてつくってしまったまちを個人の努力で田園都市化することは可能なアプローチのように思います。例えば、COVID-19終息後に、あのとき体験した働き方はありだよねといってみんなのビジョンをかき立て、共感してくれた100人が自宅事務所を開き、どこまでできるかチャレンジしてみる──、個人の小さな取組みを積分して、じわじわと広げていくようなやり方は可能かもしれないなとは思いますね。
浅子
住宅地がそういうふうに変わっていくならば、働き方の面でも、医療や介護の面でも、地域によい効果が波及していきそうですよね。実際、山崎さんは今仕事場を兼ねた自邸を新築する計画が進んでいるそうですが、どんな家を考えていらっしゃいますか。リモート会議などが増えると専用の場所も必要になりますよね。通信環境や音声、プライバシー、家族で使う空間との関係といった新しい課題も浮上すると思うのですが。
山崎
じつはすでに会議だけではなく、講演会もリモートで行う機会が増えています。数日前には後ろの書棚が露出した状態でテレビ出演することにもなりました。全国放送の地上波で自室を公開するのはもうさすがにまずいと思い、新しい自宅にはリモート会議の背景にもなるような応接の空間をつくれないかと考えはじめています。というのも、ニュース番組のスタジオにはアナウンサーの背後にちょっとした引きがあり、本棚やテーブルのような調度品が置かれていますよね。あのスペースはカメラさんがピントを合わせやすいように被写界深度をつくる目的もあるのですが、同時に視聴者にとって好ましい奥行感も生み出しています。もし自宅にもそういう場所があれば、打ち合わせや取材に対応できるうえ、リモート講演会でも聴講者に落ち着いて話を聞いてもらえる。テレビ番組と違うのは、セットではなく実際に使えるところです。
浅子
それはおもしろい! しかし、この状況下で行動に移すのも早いですね。
山崎
リモートの講演会はこれまで何度かやってみたことがあるのですが、難点は聴いている人の反応がまったく見えないことなんですよ。10分に1回くらいのペースで笑いをとろうとがんばって話してもわからない。静まり返ったこの部屋で語り続けなければならないのは普段以上に体力が必要で、1時間もやるのは本当につらいんです(笑)。
浅子
わかります(笑)。
山崎
だからそういうときは、応接スペースに近所の友だちを数人座らせておく。僕が講演中に気の利いたことを言ったら彼らにリアクションしてもらうんです。じつはそれをやりたいがためでもあるんだけど(笑)。そうでもしなければ今の状況は耐えられないと思って、すぐに土地を探し始めたんです。最大のネックだった1万冊の蔵書をなんとかしようと、松原隆一郎さんと堀部安嗣さんの『書庫を建てる』(新潮社、2014)を読み、同じようなやり方で土地を決めて、1階の事務所兼書庫と2・3階の住宅を2つの上下動線で行き来できるようにするところまでは考えました。そういうわけで今は断熱に関する本ばかり読んでいます。
浅子
楽しみですね。完成したらぜひ遊びに行かせてください。そして、今日はたっぷりお話を聞かせていただき、山崎さんはやはり設計者気質という印象を受けました。正直に言うと、コミュニティデザイナーとして活躍しはじめたころの山崎さんの活動に、ぼくは懐疑的でした。しかし、その考えも浅はかで表面的だったように思います。コミュニティデザイン=ものをつくらないと受け止められがちですが、今取り組んでおられることこそが次の時代の設計者像を体現していると言えるのかもしれません。もちろん小さな建築をコツコツとつくり続けることも大切ですが、今は大局的な視野に立ってビジョンを描くことがそれ以上に求められているように思います。山崎さんはたまたまコミュニティデザインの方に注目が集まっただけで、これから先、そのビジョンのもとに傑作をつくることだって大いにありえる。何年か後にそのような未来が来ることを個人的には期待しています。ありがとうございました。
[2020年4月24日、ZOOMにて収録]
山崎亮(やまざき・りょう)
1973年生まれ。コミュニティデザイナー、studio-L代表、社会福祉士。地域の課題を地域に住む人たち自身が解決するのを手助けする「コミュニティデザイン」を実践する。現在、慶應義塾大学特別招聘教授、NPO法人マギーズ東京理事。著書に『ケアするまちのデザイン』(医学書院、2019)、『コミュニティデザインの源流』(太田出版、2016)ほか。
浅子佳英(あさこ・よしひで)
1972年生まれ。建築家、デザイナー。2010年東浩紀とともにコンテクスチュアズ設立、2012年退社。作品=《gray》(2015)、「八戸市新美術館設計案」(共同設計=西澤徹夫)ほか。共著=『TOKYOインテリアツアー』(LIXIL出版、2016)、『B面がA面にかわるとき[増補版]』(鹿島出版会、2016)ほか。
このコラムの関連キーワード
公開日:2020年05月29日

