インタビュー 5
コロナ禍以降に再考する、健康な住まい
西沢大良(建築家、西沢大良建築設計事務所) 聞き手:中川エリカ(建築家、中川エリカ建築設計事務所)+浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)

左から、中川エリカ氏、西沢大良氏、浅子佳英氏
これまでの暮らしとこれからの暮らし
浅子佳英
今日は、西沢大良さんにお話をうかがいます。この約2年間、COVID-19とそれに右往左往する人々によって私たちの住まい方は大きく揺さぶられましたよね。しかし、その原因の本質はじつはCOVID-19ではないと思うんです。以前から、私たちの社会や住まい方は問題を抱えていました。にもかかわらず、一向に改善を続けないままその場しのぎで対処してきた。それがコロナ禍で、解決すべき問題だったことが炙り出されただけなのではないか。そして、三密に代表されるように、これは基本的に都市の問題です。そこで今日は、「現代都市のための9か条──近代都市の9つの欠陥」(『新建築』2011年10月、2012年5月号)などを執筆されている西沢大良さんと一緒に、このような大きな社会の変化が起こったときに私たちは住まいはどうなっていくのか、その辺りを議論できればと思います。
中川エリカ
まずは、コロナ禍における、住空間や暮らし方についての新たな発見や変化についてお聞かせください。地球上の誰もが強制的に働き方や暮らし方を変えざるをえない状況になり、西沢さんも自宅で過ごす時間が格段に増えたと思います。自宅に身を置き続けるという体験によって、暮らしに対する価値観や住宅設計に対する姿勢に変化はありましたか。もしあったとすれば、具体的な変化について教えてください。
西沢大良
2020年から自宅で過ごす時間が増えるなかで、気づいたことがひとつあります。それは、機能的に設計された場所ほど感染リスクが高い、ということです。例えば独立住宅の場合、トイレや浴室や洗面室、玄関や廊下などです。集合住宅の場合は、エレベーターや階段室や共用廊下です。これらの場所は、それなしでは近代生活が成り立たないような、機能的な空間ですね。そういう場所ほど家族メンバー同士、住民同士の感染リスクが高くなってしまう。
つまり極端な言い方をすれば、機能的であればあるほど命を落とす危険が出てきた、と言えなくもないわけです。あるいは近代的であればあるほど命を落とす危険がある、というような状況です。今日の独立住宅や集合住宅も、近代住宅の典型ですから、非常にまずい状況です。住宅は、体調が悪くても帰る場所だから、自宅で命が危険に晒されるようではどうにもならないです。人類史上、そんな住宅は続いた試しがないですね。
よくよく考えてみれば、もともと近代住宅の起源は、19世紀のスラムに生じた感染症や衛生問題、あるいは環境汚染を、時間をかけて解決していくなかで生み出されたわけです。当時の都市部もチフスやコレラなどの感染症に悩まされていて、街区単位でロックダウンが続出したという意味では、現在と似ています。ところが、20世紀初頭にそれらの感染症を制圧したことで危機感が薄れ、その後は近代住宅をもっぱら機能的に洗練するだけになり、ふと気づくと新たな感染症に対して無防備になっていた、というのが今の状況だと思います。おそらく今後の建築家は、あらためて住宅を命の危険のない場所に変えていくことになるだろうと思います。そこにいるだけで身体の失調が修復されるとか、自ずと健康になるように、住宅を組み立て直すことになるでしょう。
中川
先ほど、機能的な場所、もっと言えば機能的な共有部ほどリスクが高いというご指摘がありましたが、それはつまり、これまでの機能性とは異なる合理性があるはずで、それを目指すべきだというご指摘ですね。西沢さんは「〈良質な治療薬のように効いてくる〉空間」や「〈健康になれる〉建築」といった表現をよく使われる印象がありますが、今後、具体的にどのような合理性の変化が見込まれるべきなのかを考える際に、ヒントになりそうです。
西沢
僕は2005年頃から、「近代住宅の次に現れる一般的な住宅は、住み手にとって医療的・治療的な役割を果たすものになるだろう」という話をしてきました。当時は環境ホルモンやシックハウス症候群が騒がれた時期だったんですね。ですから今のような感染症を意識していたというよりは、いわゆる現代病のこと──鬱や神経症、昼夜逆転や睡眠障害、引きこもりや糖質中毒など──を意識していました。これらの現代病は、なぜか医者がうまく治してくれないからです。それでシックハウス症候群と同じように、住環境がそれらの現代病をこじらせているのではないか、と考えるようになりました。
当時の近代住宅は、日本だけではないですが、機能性・合理性を追求するあまり、ひたすら人工的な住環境を実現するようになっていました。つまり夜も昼も同じ生活をしましょう、夏も冬も同じ生活をしましょう、それどころか北米でも日本でも中国でも同じ生活をしましょう、だってそのほうが機能的で合理的だから、という考え方。この考え方でいくと、家のなかから自然の影響を取り除くことになりますね。空調や照明、建材やプランニングなどのあらゆる手段を通じて、人工的な住環境を実現していくことになる。ただし、住環境をあまりに人工的にしてしまうと、家のなかの最後の自然の産物であるところの人間の身体が、壊れ始めることになる。ちょうど水槽の水質によって魚が病気になるように、住環境によって人間が病気になっている恐れがある、ということです。それで僕は、機能的な近代住宅の次には、医療的・治療的な住宅が必要になるだろう、と言うようになりました。
その数年後、東日本大震災が起きたとき、別の角度からこのことを考えさせられました。被災地における被曝の問題のことです。あれだけ放射能が放出されてしまうと、屋外での被爆を阻止できず、建物のなかで被爆を阻止するしかないです。それ以降、住宅はもちろんですが、保育園や学校、図書館や医療施設、福祉施設なども、いずれは〈医療的・治療的〉な室環境にせざるをえなくなるだろう、と考えるようになりました。
今回の感染症も、その問題がかたちを変えてやってきたように感じています。感染症や被爆、また先述の現代病は、どれも命にかかわる問題です。この問題を、近代住宅で解決できたらいいのですが、残念ながらそれはできないだろうと思います。ではどうするかについて、私たち専門家、特にインディペンデントな建築家は、少しずつでも考えないといけないと思っています。
浅子
たしかに今回は、モダニズム的な建築ほど感染リスクの高い危険な場所となったし、機能的な場所にそれが顕著に現れていますね。政府は、飲食店を感染確率の高い場所として強く規制しましたが、じつは福祉施設での感染が最も高いとするデータもあります。福祉施設は、まさに近代計画的な産物だと言える。福祉施設のほかに感染確立が高かったのは、学校やオフィスでした。しかし、建築的プログラムで見れば最もモダニズム的ではない飲食店だけが狙い撃ちにされた。これは、建築的な問題でもありますが、ほかには適切な規制をかけなかった政治や、それを止められなかった社会にも大きな問題があるように思いました。
設計の原風景
中川
このインタビュー・シリーズでは、「建築家が住まいを考えるときには、幼い頃の体験や原風景が少なからず影響を与えているのではないか」という仮説を立ててお話を伺っています。これは、原風景と設計における実践の関係を、各世代の建築家の問題意識と合わせて考察してみたい、という狙いもあります。西沢さんは設計において、配置図と断面図でのスタディを特に大事にしていて、とてもこだわりを感じます。その姿勢はどのようにして培われたのでしょうか。幼少期の住まいや、そこで印象的だった体験などとともに教えてください。
西沢
以前に子どもの頃の話をしたことが一度あります。2007年だったと思いますが、東京ガスの「SUMIKA Project」(スミカプロジェクト)に指名され、私を含めた4人の建築家(ほかに藤森照信さん、伊東豊雄さん、藤本壮介さん)が栃木県宇都宮市に1棟ずつ実験住宅を設計しました。私が設計したのは《宇都宮のハウス》(2008)という、約70平米のほぼワンルームの平屋の住宅です。全体が光を透す屋根スラブで覆われていて、朝はベッドに、昼はキッチンに、強い光が落ちてくるようになっている。すると朝は光を浴びて目を覚まし、数時間すると今度はキッチンが光で輝き出して、「ああ昼食の時間か」と気づいて調理をすると言う想定です。家のなかで光をたどっていくと、生活リズムができあがり、昼夜逆転が治ったり、体内時計が整うという住宅です。


西沢大良《宇都宮のハウス》(2008)
ともに写真提供=東京ガス株式会社/撮影=小川重雄
この住宅が竣工した時の公開シンポジウムで、私の設計プロセスを半年あまり隣で見てきた藤森さんが、「なぜああいう空間になるんだ」「ずっと隣で見てたがさっぱりわからなかったぞ」と、しつこく説明を求めてきたんですね。最初は適当に受け流していましたが、あまりに何度も問い詰められているうちに、ふと思い出して子ども時代の経験を話したんです。
僕が生まれ育った1960年代の公団の団地には、冷暖房設備がなかったんですね。断熱材もないんです。だから夏は、ものすごく暑いわけです。家の中にいても外に出ても、とてつもなく暑いのです。当時、エアコンのある建物は銀行だけでしたが、小学生は警備員さんにつまみ出されてしまうから、冷房にはありつけない。となると、水を探すことになるんですね。プールに入れると聞けば、どこまででも自転車で行きました。それでプールに着くと、泳いだりせずに、ひたすら潜水をしていました。身体を冷やすことが目的だから、プールの一番深い場所まで潜って、息が続く限り寝そべっているわけです(笑)。たまに上に上がって呼吸をして、また水底へ潜って仰向けに寝そべって、身体を芯まで冷やしている(笑)。そのとき、プールの底から水を通して見た空の光や景色が好きだったという話を、そのシンポジウムの席上でしたんです。すると藤森さんは、「たしかにお前の《宇都宮のハウス》や静岡の《駿府教会》(2008)は、水中から上を見た景色に似ているな」「それを最初に言ってくれ。そういうことならよくわかる」と言った。伊東さんも「その水の話を最初にしたほうがいい」とか言っていて(笑)。
僕としては8歳頃の話なので、あれが《宇都宮のハウス》の原因だと言われると、反論したい気持ちもないわけではないんですけどね。その後もいろいろ経験したわけですよ。高校や大学にも行ったし、アトリエに入って修業もしたのに、8歳で空間の質が決まっていたと言われると、ちょっと切ないですね(笑)。
浅子
そのお話だけを聞くと、水の中での視覚的な体験よりも、エアコンがなくて冷気を求めてさまよっていた動物的な体験のほうが、西沢さんの設計に大きく影響しているように思います。というのも、初期の作品は違いますが、近年の西沢さんの作品には、非常に環境的あるいは設備的な面からのアプローチが強く感じられるので。
西沢
そう言えば、プールのない日は、日陰を探して街をさまよっていました。昔の団地って、1階の床スラブが地面から90cmくらい浮いていて、バルコニーの下に空間があったでしょう。あそこは早朝は日陰で、芝生もあって、子どもが身体を冷やすには最適なんですね(笑)。ただ、30分もすると太陽が動いて日が差し込んできて、冷たい日陰が逃げていってしまうから、その日陰を追いかけることになるのです。街のなかを犬のように移動しながら涼んでいましたね(笑)。
中川
日陰を求め、自ら快適な居場所を求めて移動していったという今のお話は、まさに《宇都宮のハウス》で、時間ごとにライフスタイルに合った居場所に光が指すという設計に結びついていますね。
西沢
たしかに似てますね(笑)。とはいえ、1960年代の子どもがみんなこういう住宅を設計しているわけじゃないので、私の実力も少しはあると思うんですよ(笑)。
浅子
当時の人々がみんな西沢さんみたいに冷気と日陰を追い求めてプールに沈んだりさまよい歩いていたわけでもないですしね(笑)。
配置図と断面図へのこだわりについても聞かせてください。2018年に、西沢さんは雑誌『住宅特集』で、座談月評を担当されていました。月評の最後に公開でのイベントがあり聞きに行ったのですが、そこで西沢さんは、あらゆる創作活動のなかで、建築オリジナルのものは何だろうと考えたときに、それは「サイズ」じゃないかと話されていました。例えば、彫刻で5mの作品は大きいと感じるけれど、建築のスケールでは、それはとても小さい。僕たちは住宅なんて小規模なものだと感じているし、軽々しく設計しているけれど、よく考えれば、街のなかに人の手であれだけ大きな構築物を作るということはなかなかすごいことなんですよね。そうしたことを最も感じるのが街との関係を描く配置図であり、人のかたちやスケールとの対比が出る断面図なんだ、といったことを話されていて強く記憶に残っています。
西沢
あの公開イベントでは、建築とはサイズの芸術であり、寸法の芸術である、と言ったと思います。サイズや寸法の問題とは、例えば柱が、人の身体の隣に立ちあがった時、その太さや細さが人を快適にしたり不快にするという問題です。あるいは部屋の天井高なら天井高が、人を快適にしたり不快にしたりするという問題です。断面図には人体を描き込めるので、この問題をスタディしやすいのですが、平面図だと難しい。平面図の場合、部屋の配列とか動線の効率性などの、言語的な空間把握に向いていると思います。その分、住み手の身体感覚をつかみにくいです。
中川
私の事務所でも、断面図から設計することが多いのですが、それは、より体験的な視点で設計ができる予感があるからです。人間を断面図の中に立たせて快適さを検証するというお話は、とても共感しました。
西沢
10年くらい前に、必要があって学生時代の図面を大学に見に行ったんですが、卒業設計だけでなく、最初の設計課題から断面でした。僕の母校の東京工業大学では3年生で初めて設計課題をしますが、最初の設計課題はギャラリーの設計でした。僕の案は2階建てでしたが、地上2階建てではなく、地下1階・地上1階の2階建てでした。理由はおぼろげに覚えていますが、ギャラリーは展示室の光が大事だから、光の状態が違う2つの展示室を設計しようとしたと思います。その図面では、地上の展示室が自然採光で、地下の展示室が人工照明になっていました。
2作目は、10mキューブを住宅に仕立てるという、よくある設計課題です。これも2階建ての案でしたが、断面図を見ると、1階と2階のあいだのスラブが斜めになっている。1階には、一部に水回りがあるほかは、大半がLDKになっていて、天井が片流れ状の斜めスラブで、高い方のハイサイドライトから光が落ちてくる。2階はほぼ屋外で、斜めのスラブに沿って日本庭園のような庭をつくっていて、その一部に和室が450mm浮いていました。
これらの断面図を見たとき、同行していた所員に「今とおんなじですね」と言われました(笑)。自分としても「まったく進歩していないな」という忸怩たる思いがありました(笑)。最初から断面のことばかり考えていたみたいです。
中川
配置図に関する興味はいつから出てきたのですか。
西沢
それは独立した時期が平成不況期で、狭小住宅しか立たなくなったことが影響している気がします。それ以前の修業時代は、バブル景気のおかげでさまざまな規模の設計に携わることができたんです。住宅も、修業時代は延60坪などと規模も大きく、総工費も高額でしたが、独立後は延床20坪台になり、総工費も大きく下がりました。ワンフロア10坪程度で家族4人が暮らすとなれば、どうしてもLDKを広くするしかなく、細かいプランニングの腕を見せる余地がなくなった。そのかわり、配置には工夫の余地があったので、配置図に時間をかけるようになりました。僕の初期の住宅作品は、ほとんど配置図と断面図のスタディだけでできていると思います。
浅子
住宅ではないですが、《今治港駐輪施設》(2017)も驚きました。本当に、配置と断面だけでできている。厳密にデザインされ、ディテールもよくできているので、駐輪場なのにひとつの建築作品になっている。しかも、感動したのは、自転車が自然ときれいに並んで停められるような設計がなされていたことです。

西沢大良《今治港駐輪施設》(2017)
撮影=浅子佳英
西沢
あの駐輪場は、地元の方々しか行かない四国の港にあって、建築界では浅子さんしか内観を見ていないんですね。一般的に言って駐輪場の空間は、学校でも駅前でもそうですが、出入口付近に自転車がぐちゃぐちゃに折り重なっていて、僕は昔から「嫌な空間だなあ」「この空間現象は何とかならんのか」と思っていました。駐輪場を設計する立場になったとき、あの空間現象を阻止するにはどうしたらよいかを考えました。利用者が出入口だけでなく奥にも自ずと停めるようにするには、何をどうしておけばいいか。《今治港駐輪施設》の場合、長さ20m弱の平屋のボリュームにして、出入口を両端に設けました。そして天井から光が1.8mピッチで床に落ちてきて、時間とともに明るい場所が移動していくようにした。すると、人はなるべく明るい場所に停めたいので、1.8mピッチで自転車を停めていって、船に乗船する。そして1時間後に次の船が出る頃は、光の位置がずれているから、次の乗客たちが明るい場所に1.8mピッチで自転車を停めて、船に乗船する。だから出入口に自転車が集中するような空間現象が起こらない。自分でもこれは良い仕事だと思って、日本中の駐輪場で真似してほしいと思っているのですが、誰も見に来ないから広まっていませんね(笑)。
浅子
西沢さんの配置図へのこだわりにどれくらい影響したのかはわかりませんが、数々のリサーチを塚本由晴さんと一緒に『現代住宅研究』(LIXIL出版、2004)という書籍にまとめられましたよね。西沢さんは学生の頃、地図のコピーを頼りにたくさんの住宅作品を見に行ったとおっしゃっていました。名作住宅を地図のなかにプロットし、実際に歩いて探しながら見に行き、それらを自分のなかにアーカイブしていくという体験から、住宅と周辺環境の関係が相対化され、さまざまな気づきを得られたのではないかと思うのですがいかがですか。
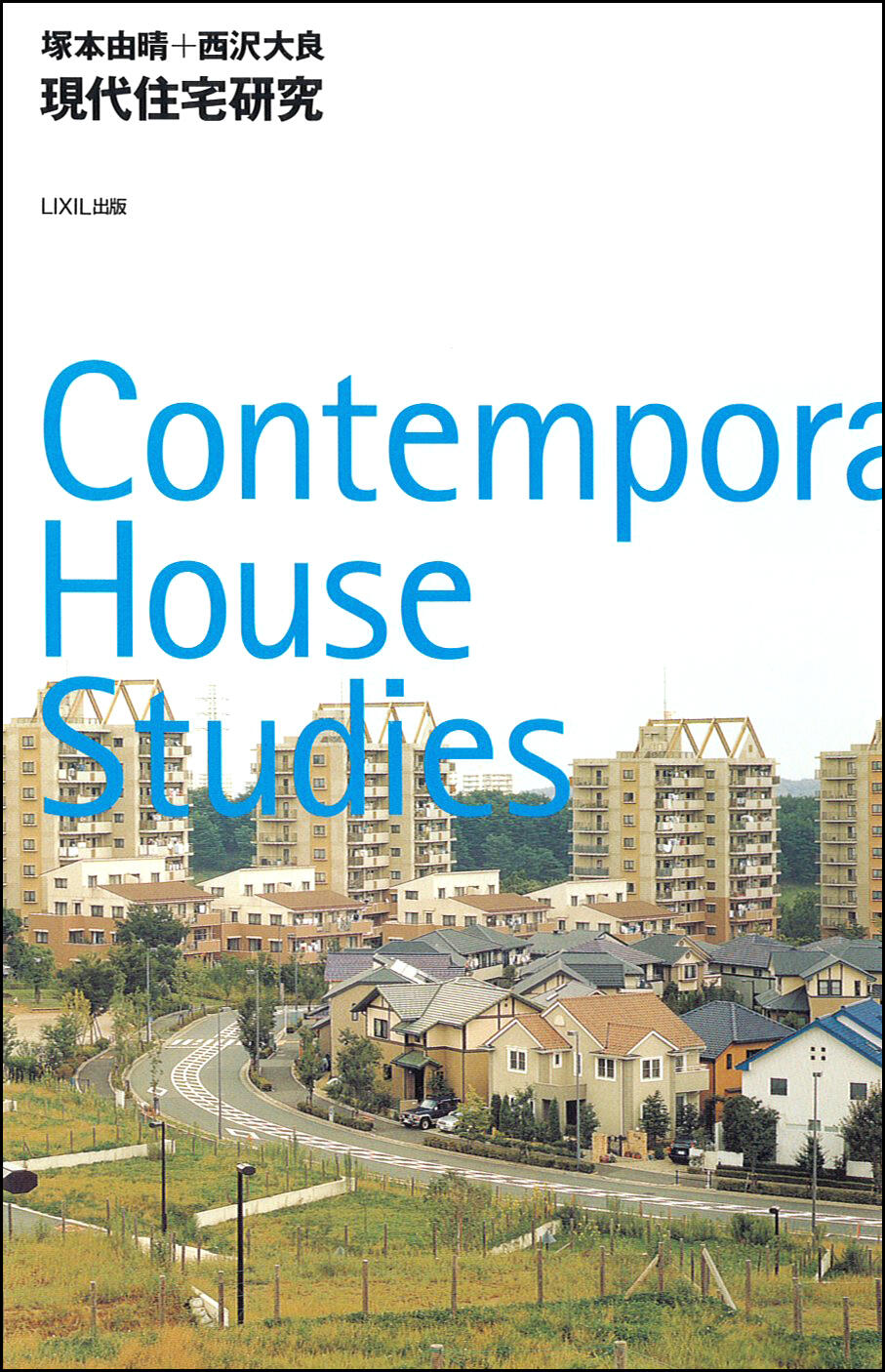
塚本由晴+西沢大良『現代住宅研究』
西沢
たしかに学生時代は授業にも出ないで、ひたすら住宅を見に行きました。篠原一男さんや坂本一成さん、あるいは清家清さんといった東京工業大学の先生方が住宅を作っておられたので、そういう名作を見て回ったんですね。当時は配置を意識していたかはわかりませんが、通りを歩いていて、建築の出現のしかたに驚くという経験を何度もしました。それに、住まい手のご厚意で室内に入れてもらえた時は、じつによくできているなと、普通の家屋とはまったく別物だなと、建築家の力量を感じました。僕は今でも住宅を設計するときは、当時の記憶だけで作っています。
このコラムの関連キーワード
公開日:2021年12月22日

